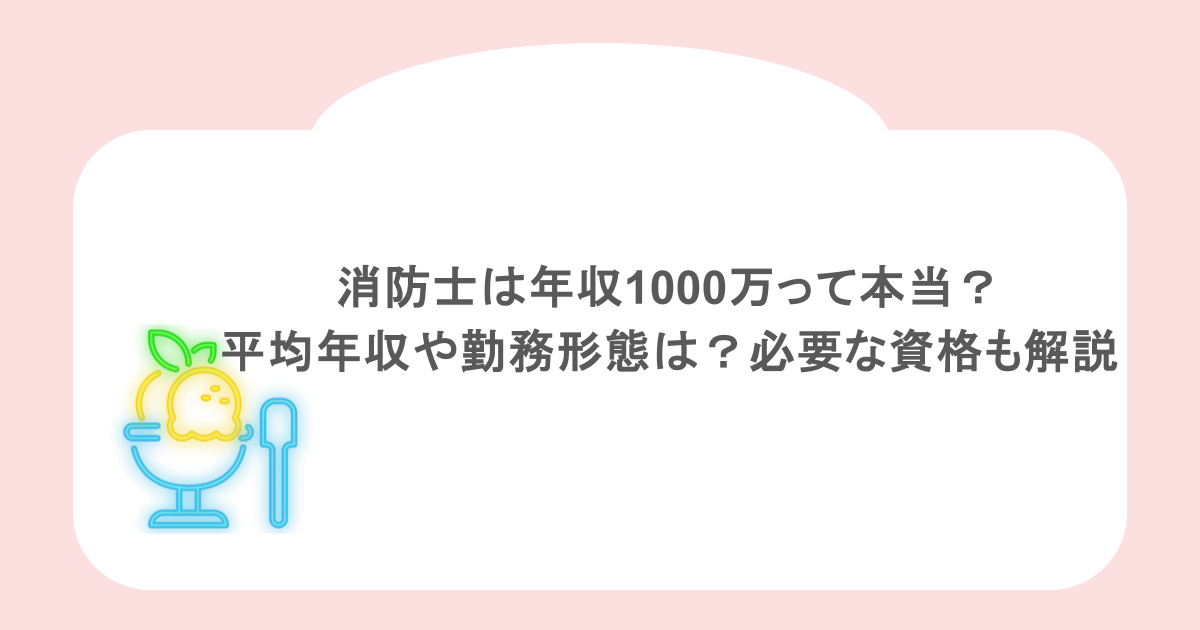消防士の仕事に興味を持っている方の中には、「消防士は年収1000万円って可能なの?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、消防士の現実的な年収事情から、意外と知られていない勤務形態、そして採用に必要な資格まで、元消防士の声も交えながら詳しく解説していきます。
消防士の平均年収はどれくらい?
まずは気になる年収の話からスタートしましょう。
消防士の現実的な給与水準
消防士は地方公務員として働くため、給与は各自治体の給与条例に基づいて支払われます。平均的な年収は400万円から600万円程度が一般的です。
勤続年数や階級、勤務地によって差はありますが、新人の頃は年収300万円台からスタートし、経験を積むにつれて徐々に上がっていく仕組みになっています。ただし、夜勤手当や特殊勤務手当などが加算されるため、同じ公務員の中でも事務職より若干高めの水準になることもあります。
消防士の年収1000万円は本当に可能なのか
結論から言うと、消防士が年収1000万円を達成するのは極めて難しいのが現実です。
少子高齢化による財政難の影響で、公務員全体の給与水準が抑えられる傾向にあります。消防士は命の危険と隣り合わせの仕事にもかかわらず、給与体系は事務職の公務員とほぼ変わらないケースも少なくありません。年功序列で基本給が上がっても、手当がカットされてしまえば、トータルの年収は思ったほど伸びないというジレンマがあるのです。
ちなみに、国税庁のデータによれば、日本で年収1000万円以上を稼いでいる人の割合は全体のわずか5.4%。男性だけで見ても8.4%程度です。消防士として本業一本で年収1000万円を目指すのは、かなりハードルが高いと考えておいたほうがよいでしょう。
消防士が年収1000万円を実現する2つの方法
それでも高収入を目指したいという方のために、現実的な選択肢をご紹介します。
民間企業への転職でキャリアチェンジ
消防士から民間企業、特に外資系企業への転職は、年収を大幅にアップさせる有力な選択肢です。
実際に警察官から外資系企業に転職して年収1000万円を超えた例や、製造業からIT業界の外資系企業に転身して高年収を実現した事例も報告されています。消防士のキャリアは防災分野や建築業界で高く評価されるため、適切な業界を選べば転職市場で大きな強みになります。
特に20代から30代前半であれば、未経験の業界でも実績を積みやすく、その後さらなるキャリアアップも狙いやすいでしょう。
家族名義での副業という選択肢
もう一つの方法は、家族名義で副業に取り組むアプローチです。
公務員は副業が原則禁止されていますが、家族が事業主となり、その手伝いをするという形であれば法律に抵触しません。YouTube、ブログ、物品販売など、拡張性のある副業に成功すれば、本業の安定収入と組み合わせて高収入を実現できる可能性があります。
ただし、副業で成功するのは簡単ではありません。30代後半以降で転職が難しくなってきた方には検討の余地がありますが、再現性という点では転職のほうが現実的かもしれません。
消防士の勤務形態を詳しく解説
続いて、消防士の働き方について見ていきましょう。
基本は24時間勤務体制
消防士の勤務は、多くの場合「夜勤・非番・夜勤・非番・週休・週休」というサイクルで回っています。
夜勤は朝8時頃から翌朝8時頃までの24時間勤務です。この間、火災や救急などの緊急出動に備えながら、訓練や車両点検、事務作業なども行います。非番は休みですが、大規模災害時には招集がかかることもあります。
この勤務体系は体力的にハードですが、まとまった休みが取れるというメリットもあります。
日勤勤務も存在する
意外と知られていませんが、消防士には朝8時から夜7時頃までの日勤勤務もあります。
日勤勤務の消防士は、火災予防のための施設点検や指導、地域住民への防災啓発活動、訓練の実施、消防車両の点検整備、事務作業など、緊急出動以外の重要な業務を担当します。火災を未然に防ぐ予防活動は、実際の消火活動と同じくらい大切な仕事なのです。
消防署や担当部署によって日勤と夜勤の割合は異なりますが、キャリアを積むにつれて予防業務や管理業務に携わる機会が増えていくケースも多くなっています。
消防士になるために必要な資格
ここからは、消防士を目指す方が気になる資格について解説します。
採用に必要な資格は「なし」
驚くかもしれませんが、消防士になるために特別な資格は一切必要ありません。
公務員試験に合格さえすれば、無資格でも消防士として働き始めることができます。現役の消防士によると「採用試験で資格の有無が合否を大きく左右することはない」とのこと。試験対策にしっかり時間を使ったほうが、より合格に近づけるそうです。
強いて言えば、普通自動車免許があると入職後すぐに役立ちますが、これも必須ではありません。
あると役立つ資格
とはいえ、採用後にキャリアの幅を広げたいなら、いくつかの資格取得を検討する価値はあります。
救急救命士は、大学や専門学校で取得するか、消防士になってから取得するかの2つの方法があります。かつては希少性が高い資格でしたが、現在は取得者が増えたため、採用時の評価はそれほど高くありません。
大型自動車免許は、はしご車や救助工作車などの大型車両を運転するために必要です。取得費用は約30万円と高額で、全額自己負担となるケースがほとんど。それでも「子どもの頃からはしご車に乗るのが夢だった」という職員は積極的に取得しています。
小型船舶免許や潜水士の資格は、海や川、湖がある地域の水難救助隊で活躍できます。小型移動式クレーン運転士は救助工作車のクレーン操作に、危険物取扱者は燃料の取り扱いや施設の審査業務に役立ちます。
予防技術検定は、防火査察や消防用設備、危険物施設の指導を行う際に重宝される資格です。近年は3種類すべてを取得する職員が増えてきています。
消防士という仕事を選ぶ前に知っておきたいこと
最後に、消防士を目指す方へのアドバイスをお伝えします。
給与だけでなく、やりがいも重要
確かに消防士の給与は、仕事の危険度や責任の重さに見合っていないと感じる声もあります。
しかし、地域の安全を守り、人の命を救うという仕事の意義は、お金では測れない価値があります。緊急時に頼られる存在であることへの誇り、訓練で身につけた技術を実際の現場で活かせる達成感、チームで困難を乗り越える一体感など、消防士ならではのやりがいは数多くあります。
高収入を目指すなら転職や副業という選択肢もありますが、消防士という職業そのものに魅力を感じるかどうかが、最も大切な判断基準になるでしょう。
最後に
消防士の仕事について、この記事で基本的な情報はお伝えしました。
でも、実際の雰囲気や職場の様子は、やはり自分の目で見てみないとわかりません。多くの消防署では見学を受け付けているので、興味がある方はぜひ問い合わせてみてください。現役の消防士と話すことで、インターネットでは得られないリアルな情報が手に入るはずです。
消防士は地域社会にとって欠かせない存在です。給与面での課題はありますが、それを補って余りある社会的意義のある仕事だと言えるでしょう。この記事が、あなたのキャリア選択の参考になれば幸いです。